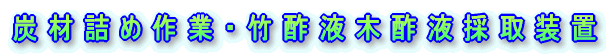
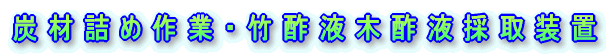
| 炭を焼くには、炭焼き窯に炭材を詰め込まなければなりません。今回の炭材は、間伐後しばらく放置されていた古い竹材です。窯のサイズに会わせて切断し、窯の中に整然と詰め込みます。 |
| 縦・横・斜め?試行錯誤の実験ですが、最も効率の良い炭の焼き方を探索してゆきます。詰め方は色々ありますが、初窯の火入れに向けてこの日は横詰めの実験です。窯のふたをして、隙間を粘土で目土張りし、断熱用の砂を盛って窯を密封します。 |
| 長い煙突のようなステンレスの筒は、化学実験の蒸留に使うコンデンサーと同じような働きをします。炭焼き窯から出た煙の留分を冷却し、竹酢液や木酢液を採取する装置です。煙突の上に帽子をかぶせ、長い煙突(コンデンサー)をつなぎ、冷やされて液化した竹酢液や木酢液を竹の樋に導きます。煙突の長さや角度など、いろいろな工夫やノウハウが潜んでいる場所なのです。 |
 |
| そして、何だと思います?ペットボトルの底を切り取って、逆さにしたもの・・・簡易ろ過器を試作してみました。竹酢液や木酢液に混ざっているタール分やその他の不純物を、少しでも取り除く事ができればと、雑木林に自生するシュロの皮を、ろ過材に使ってみました。 |
| 炭焼き窯の構築 | 基礎作り | 煙突 | たき口 | 小屋完成 | 炭材詰め(この頁) |